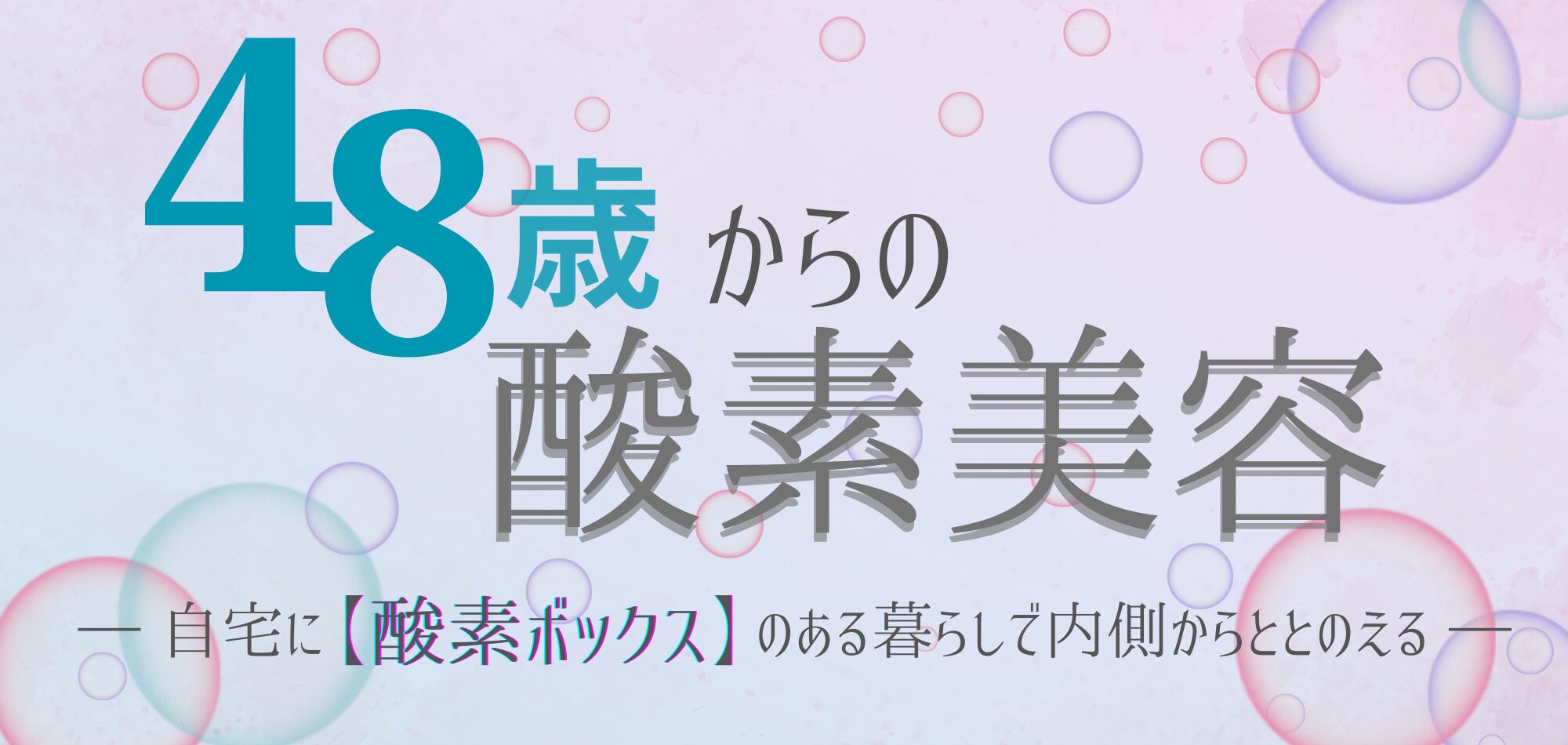.png)
糖尿病対策というと、食事や運動が真っ先に思い浮かびますよね
けれど私が日々、【酸素ボックス】サロンの現場でお客様と向き合う中で感じているのは、「酸素のめぐり」こそが、血糖コントロールだけでなく、体を整える土台だということです
【酸素ボックス】に通うことで、体が軽くなった、眠れるようになった、数値が安定してきた——
そんな変化を見せてくれる方が、本当に多いんですよ
私自身、ヘモグロビンA1cが下がり、糖尿病予備軍から抜け出せた経験があります
だからこそ、同じように血糖のことで悩んでいる方に、酸素の力を知っていただきたいと思っています
今日は、酸素ボックスを運営する立場から、「酸素」と「血糖」の深い関係についてお話しします
なぜ糖尿病は“糖”だけで語れないのか?——酸素・代謝・血流の視点から
【糖尿病対策】|なぜ?食事と運動の指導をされるのか?
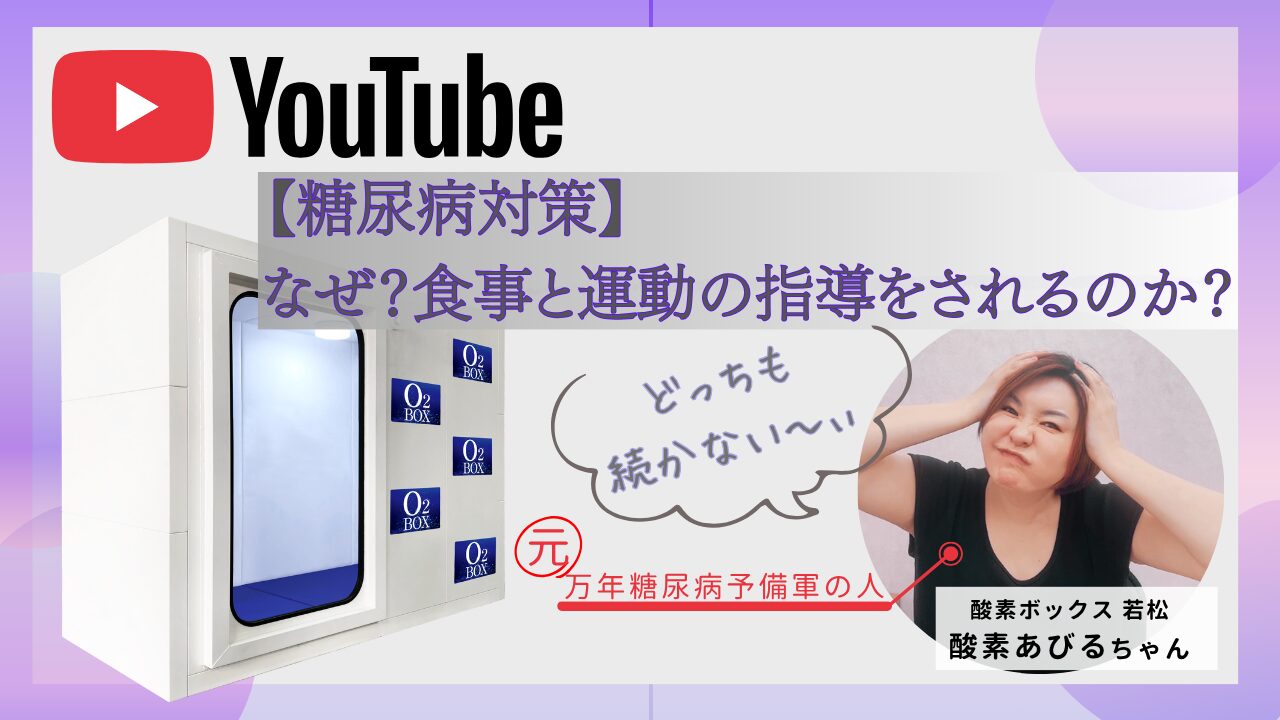
糖尿病の初期段階で必ずといっていいほど出てくるアドバイス——
「食事を見直しましょう」「運動を増やしましょう」
一見、当たり前のようでいて、なぜこの2つなのか、意外と深く考えたことがない方も多いかもしれません
理由は、糖と酸素を使う“舞台”が筋肉だからです。
筋肉は、全身で最も多くのエネルギーを消費する器官です
歩く・支える・姿勢を保つ、そのすべてに、微細な筋肉の働きが関わっています
つまり、筋肉が活発に働くほど、糖と酸素の需要が高まり、代謝が循環しやすくなるのです
食事制限は「糖の供給」を調整するアプローチ
運動は「糖の消費」と「酸素の取り込み」を高めるアプローチ
この2つがセットで勧められるのは、摂取する糖を“減らす”こと と“使う”こと、この両方のバランスをとるためなのです
しかし、ここにもうひとつ大切な視点があります
それは——酸素が足りなければ、糖は燃やせないという事実…
どんなに糖を控えても
どんなに運動をしても
体のすみずみまで酸素が届かなければ、糖はエネルギーとして完全に使われず、血液中に残ってしまうんですよ
言い換えれば、糖そのものが問題なのではなく、“酸素が届いていない体”が、糖を使いきれなくしているいことが問題なのです
糖を燃やす力=代謝の土台には、必ず酸素が関わっています
だからこそ、糖尿病対策の原点である「食事」と「運動」も、その本質は“糖をどう減らすか”ではなく、“糖をどうエネルギーに変えるか”にあります
私たちはつい、「控える」「我慢する」という方向に意識を向けがちですが、本当に必要なのは、“燃やせる体”を育てること
食事も運動も、酸素が満ちてこそ意味を持つ行為なのです
そして、現代人の多くが抱えるのは、忙しさとストレスによる「慢性的な酸素不足」
深呼吸が浅くなり、肩が固まり、血流が滞る——
それだけで糖代謝の回路は鈍くなってしまいます
だからこそ、まずは 酸素の通り道を整え、めぐる体の戻すこと
散歩、ストレッチ、呼吸、姿勢、そして酸素ボックスなど、あなたに合った方法で、酸素を体に取り戻す
糖を減らすのと同時に、酸素を増やす!
この視点が、血糖コントロールを根本から変えていく鍵なのです
【血糖コントロール】糖尿病予防には、糖代謝がカギを握っている!?
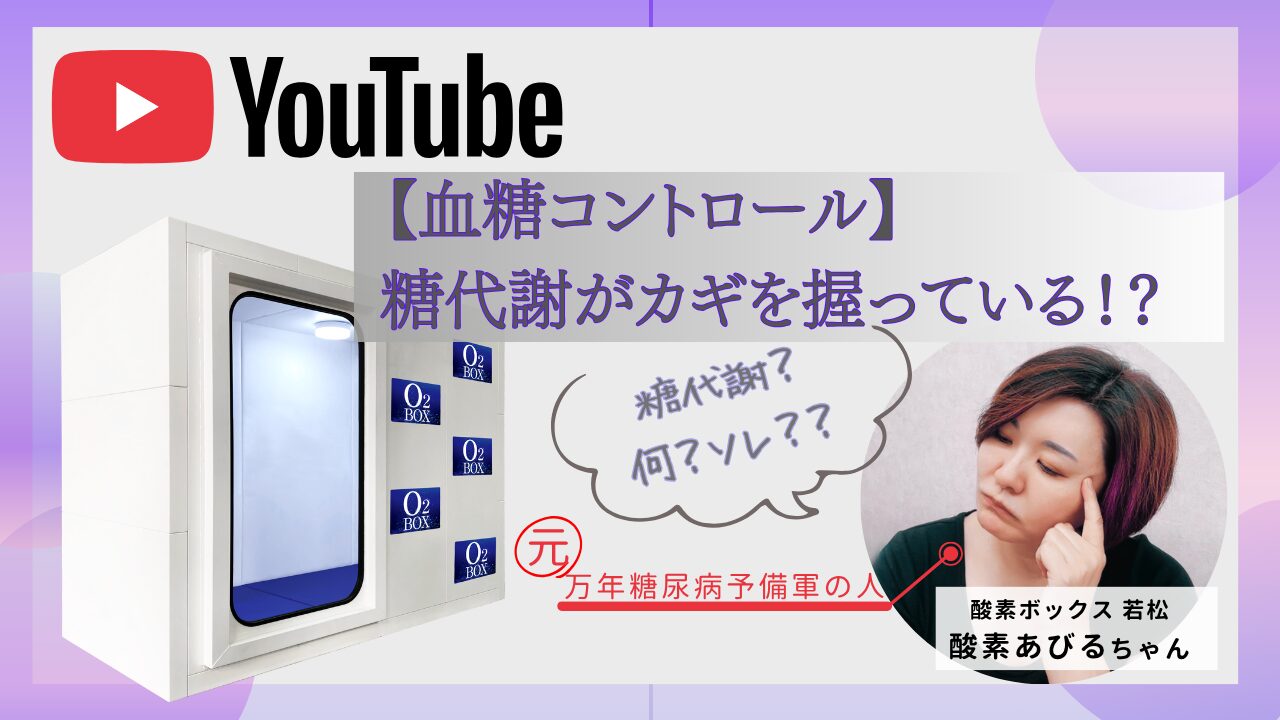
糖尿病の予防や改善で一番大切なのは、「糖をどう使うか」です
けれど、多くの人が「糖を摂らない」「運動で消費する」といった“行動”ばかりに意識を向けがちです
しかし、実際に血糖コントロールを左右しているのは、もっと根本的な部分――糖をエネルギーとして燃やせる代謝の仕組みそのものです
体の中でその仕組みを担っているのが、筋肉と脳になります
この二つは、私たちが想像する以上にエネルギーを使う器官なのです
筋肉は、全身の約40%を占める巨大な組織で、体を支え、動かし、熱を生み出しています
当然ながら、安静時に動きは少なくても、立ち上がる・歩く・姿勢を保つといった瞬間に、一気に代謝が活発になりエネルギーを消費します
そして、そのエネルギー源の主役が“糖”なのです
筋肉の中で糖が燃えることで、力と熱が生まれ、体温や基礎代謝が維持されます
一方の脳も、小さな器官ながら驚くほどのエネルギーを消費しています
体重のわずか2%しかないのに、安静時でも全エネルギーの20〜25%を使っているのです
考える・感じる・判断する——そのすべての活動に糖が使われています
そして、この糖を燃やす(エネルギーに変える)力を左右しているのが、酸素です
焚き火に例えると、薪が糖だとしたら、火を大きくしたいなら、空気(酸素)を送り込むのと同じです
酸素が足りなければ、糖は完全に燃焼せず、エネルギーとして使いきれないまま血液中に残ってしまいます
つまり、糖を減らすことよりも、糖を「うまく燃やせる体」に整えるほうが、根本的な解決になるのです
血糖値を下げる努力が報われないのは、意志や根性が足りないからではありません
燃やす仕組みが“酸素不足”で滞っているだけなので、この仕組みを整えてあげるだけで、同じ努力でも結果が変わってきます
筋肉にも脳にも、酸素が十分に届く状態をつくることが、血糖コントロールのいちばん確かな近道です
深呼吸を意識してウォーキングやストレッチなどで酸素のめぐりを良くすることから始めてみてください
努力の方向を変えると、気持ちにも余裕が生まれるだけでなく、あなたの代謝力も変わっていきますよ
血糖値を上げないコツ
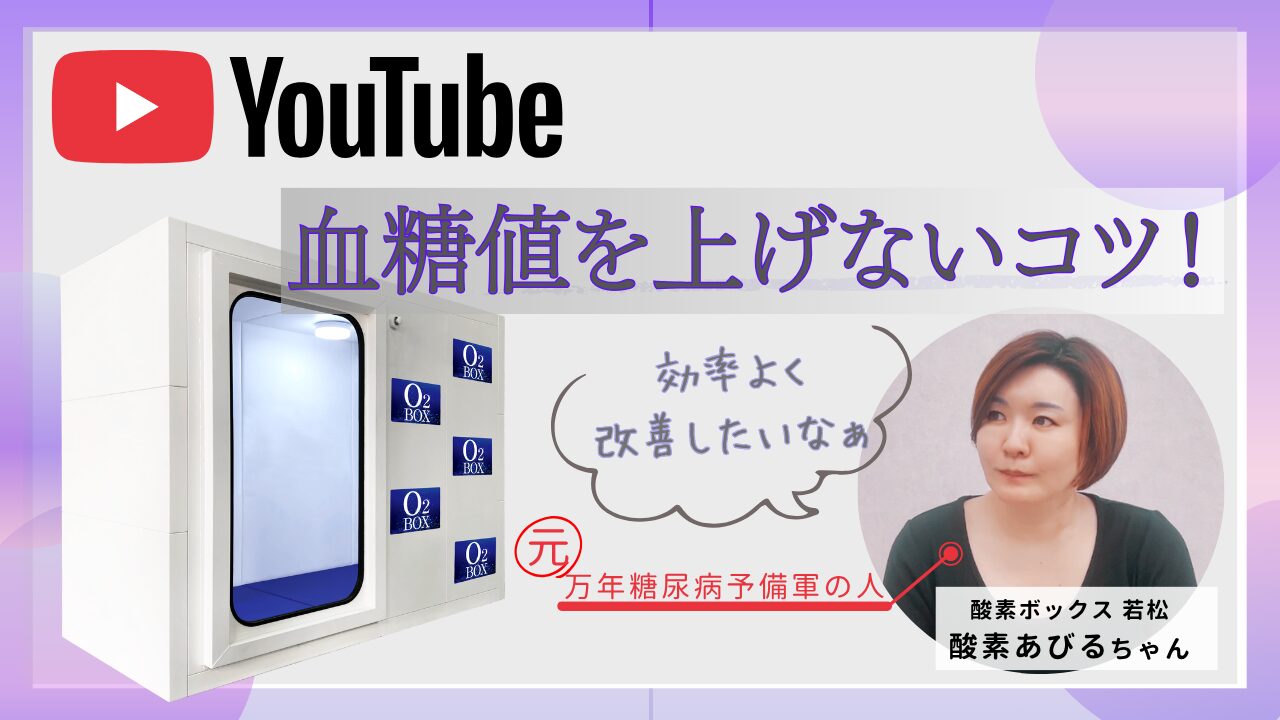
体は、糖と酸素をセットで使いながら、エネルギーに変えています
酸素が不足すると、糖をうまく燃やせず、血液中に糖が残りやすくなります
つまり、血糖値が高いというのは、「糖が多い」のではなく、「酸素が足りず、使いきれない」状態なのかもしれないということです
私自身、食事も運動もほとんど変えていないのに、ヘモグロビンA1cが6.3から5.6に下がったのは、
この仕組みが、私の知らないところで、発動しただけだと思っています
酸素がしっかり届くと、ミトコンドリアが活発に働き、糖をエネルギーとしてきちんと利用できるようになります
同じ食事でも、糖の“使われ方”が変わるということですね
酸素不足のままでは、糖が代謝されにくく、結果として血糖値が高めに推移しやすい体質をつくってしまうのです
酸素ボックスに入ると、気圧が高まり、血中の酸素分圧が上がります
血液中に溶け込む酸素量が増えることで、毛細血管のすみずみにまで酸素が届きやすくなり、体内でのエネルギー生成がスムーズになります
その結果、糖が“余る体”から“使える体”へと変わっていく…
私のヘモグロビンA1cの変化は、まさにその象徴でなのでしょう
そしてもうひとつ
血糖値を「下げる」よりも、「上げない」工夫も大切です
食後10〜20分ほど、軽く体を動かすだけで、血糖の急上昇を抑えられることはご存じでしょう…
食後は血液中に糖が増えるタイミングです
ここで筋肉を動かすと、糖が効率よく取り込まれ、エネルギーに変わります
このとき、必要なのが“酸素”です
酸素がなければ糖はうまく燃焼せず、エネルギー化できません
つまり、酸素が足りている人ほど、血糖値の上昇をやわらげやすいのです
一方で、脂肪を燃やしたいなら、食前(空腹時)の軽い運動も有効です
糖が少ない状態では、脂肪が優先的に使われるからです
ただし空腹時は血糖も低めなので、ウォーキングやストレッチなど、呼吸を乱さずにできる範囲にとどめるのが安心です
血糖を上げないコツは、食後30分以内に軽く動くこと
食後すぐではなく、消化が落ち着く20〜30分後に、深い呼吸を意識しながら歩く――それだけでも、酸素と血流がめぐり、代謝のリズムが整っていきます
生活を大きく変えなくても、酸素で満たされた体に変わるだけで、血糖コントロールは確実に変わります
糖尿病予備軍からの脱出!?【リアルガチ】
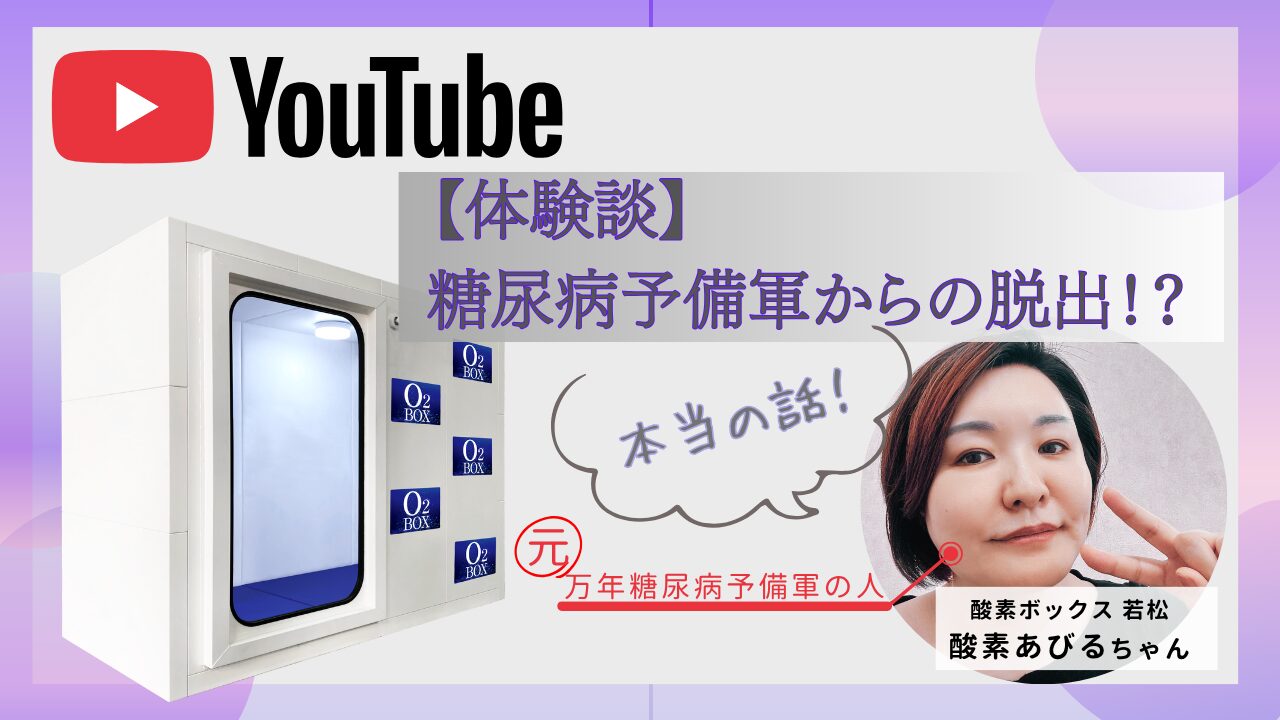
糖尿病予備軍になって、はや20年?
万年糖尿病予備軍の私は、食事も運動も、大して努力はしていませんでした
血糖値は下がりもしなければ、上りもしない。。。という、ある意味、安定を維持していました
「これでいい」と思っていました
急激に上がらなければ、それでいい…ずっと、そう思っていました
そんな、私のヘモグロビンA1cが改善したきっかけは、酸素ボックスでしょう。。。
最初は別の目的で、利用しはじめました
けれど、利用しはじめて1年後――
血液検査の結果に、思わぬ変化が現れたのです
ヘモグロビンA1cが、6.3から5.6へ下がっていたのです
正直、生活習慣はほとんど変えていません
食事は以前と同じ、運動もしていませんm
それでも、数値が変わっていました
なぜだろう?
その理由を考えたとき、見えてきたのは【酸素ボックス】でした
私たちの体は、酸素と糖をセットでエネルギーに変えていますが、酸素が不足すると、糖がうまく燃えず、血液の中に残りやすくなります
すると血糖値は高めに推移し、代謝のリズムが乱れてしまいます
一方で、酸素が十分に届く体になると、細胞が糖をきちんとエネルギーとして使えるようになり、血糖のバランスが自然と整っていくのです
【酸素ボックス】に入ると、ボックス内の気圧が上がりことで、血中の酸素分圧が高まります
すると、毛細血管のすみずみまで酸素が届きやすくなり、体の隅々でエネルギー生成がスムーズに進むのです
つまり、同じ生活をしていても、酸素が満ちている体では「糖の使われ方」が変わるということ
努力の量を増やさなくても、努力の成果が変わるのです
この変化を体験してから、私は思うようになりました
血糖コントロールは、頑張りだけで解決するものではありません
“細胞が働ける環境”を整えることが、最もシンプルで確実な近道なのだと
【合わせて読んで欲しい記事】
※医師に「糖尿病予備軍です」と言われて不安になったら読む記事
※へモグロビンA1cと酸素の関係とは?|血糖コントロールの新しい視点
【糖尿病】意外過ぎた!? 酸素との関係とヘモグロビンA1cが教えてくれる、あなたの糖代謝
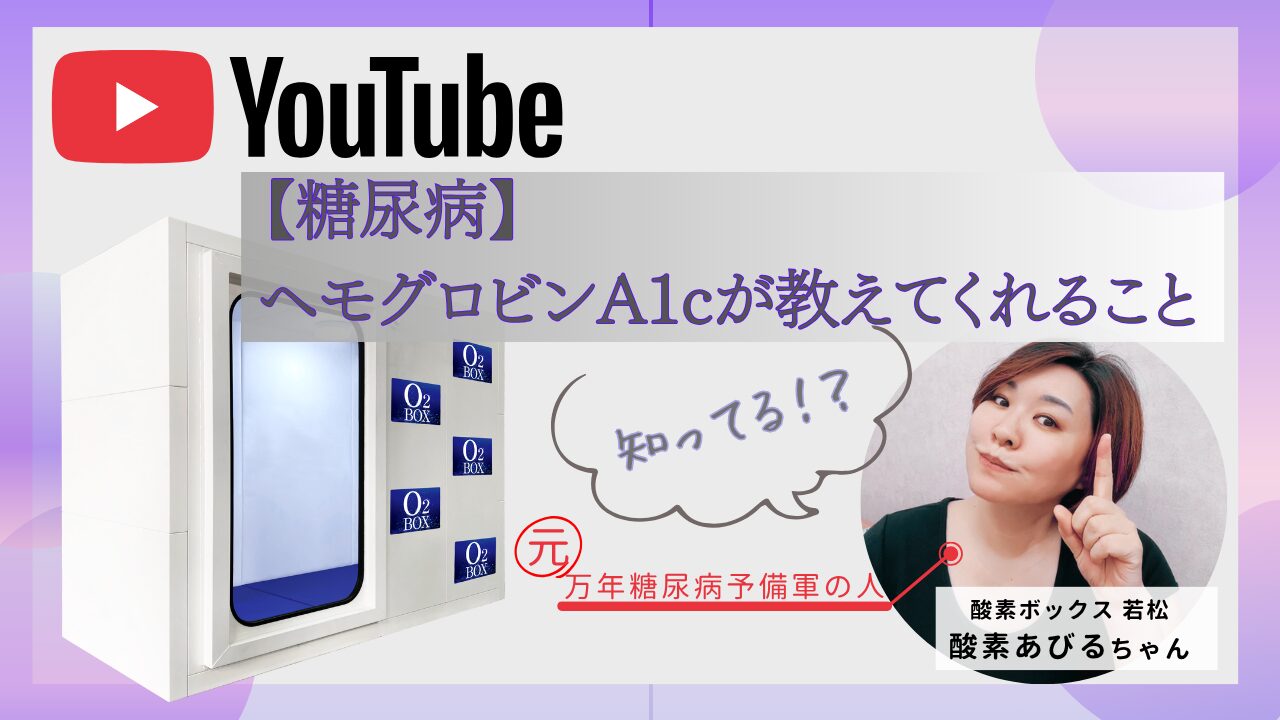
糖尿病とは、糖をエネルギーとしてうまく使えなくなる状態のことです
本来、食事で摂った糖は筋肉や細胞で燃やされ、体を動かすエネルギーになりますが、燃焼が悪くなると、血液中に糖が残りやすくなり、血糖値が高いまま推移してしまいます
このとき、血液の中にどのくらい糖が残っているのかを示す指標が「血糖値」や「ヘモグロビンA1c(エーワンシー)」です
ヘモグロビンA1cとは、赤血球の中で酸素を運ぶ役割である、たんぱく質「ヘモグロビン」に、糖がどの程度結びついているかを示す数値です
ここを見ることで、過去1〜2か月の血糖コントロールの状態がわかります
日本糖尿病学会による基準では、
-
5.7〜6.4%が「境界型(予備軍)」
-
6.5%以上が「糖尿病型」 とされています
健康診断や一般の血液検査で、比較的かんたんに調べられます
この数値は「血糖値の履歴」だけでなく、実は「酸素の通り道」とも深く関係しています
ヘモグロビンは、もともとは全身に酸素を運ぶ役割を担っています
血糖が高い状態では、糖化したヘモグロビンが増え、酸素を届ける能力が低下するため、組織への酸素供給が悪くなくなるのです
酸素が届かないと、筋肉や細胞の中で糖が燃えにくくなり、エネルギー生成の効率が落ちることで、さらに糖が余って血糖が上がる——という悪循環が生まれます
逆に、酸素がしっかり届く体になると、細胞が糖をエネルギーとして正しく使えるようになり、血糖のコントロールがしやすくなります
糖尿病のケアで大切なのは、「糖を減らすこと」だけではなく、糖を“燃やせる体”に整える、つまり代謝の土台をつくることです
そして、その土台づくりを助けてくれるのが、【酸素ボックス】なのです
【酸素ボックス】で、気圧を高めることで血中の酸素分圧が上がり、毛細血管のすみずみまで酸素が行き渡りやすくなります
酸素が十分に届けば、糖はスムーズに使われ、余りにくくなり、それが、ヘモグロビンA1cという数値にも反映されていくのです
糖と酸素は、切っても切れない関係なのです
どちらが欠けても、体は正しくエネルギーを生み出せません
血糖コントロールのカギは、いつだって「酸素の流れ」の中にあるのです
血糖を乱すのは“糖”だけじゃない——生活習慣に潜む3つのリスクを深掘り
睡眠の質が悪いとどうなる!? 糖尿病と睡眠の深い関係
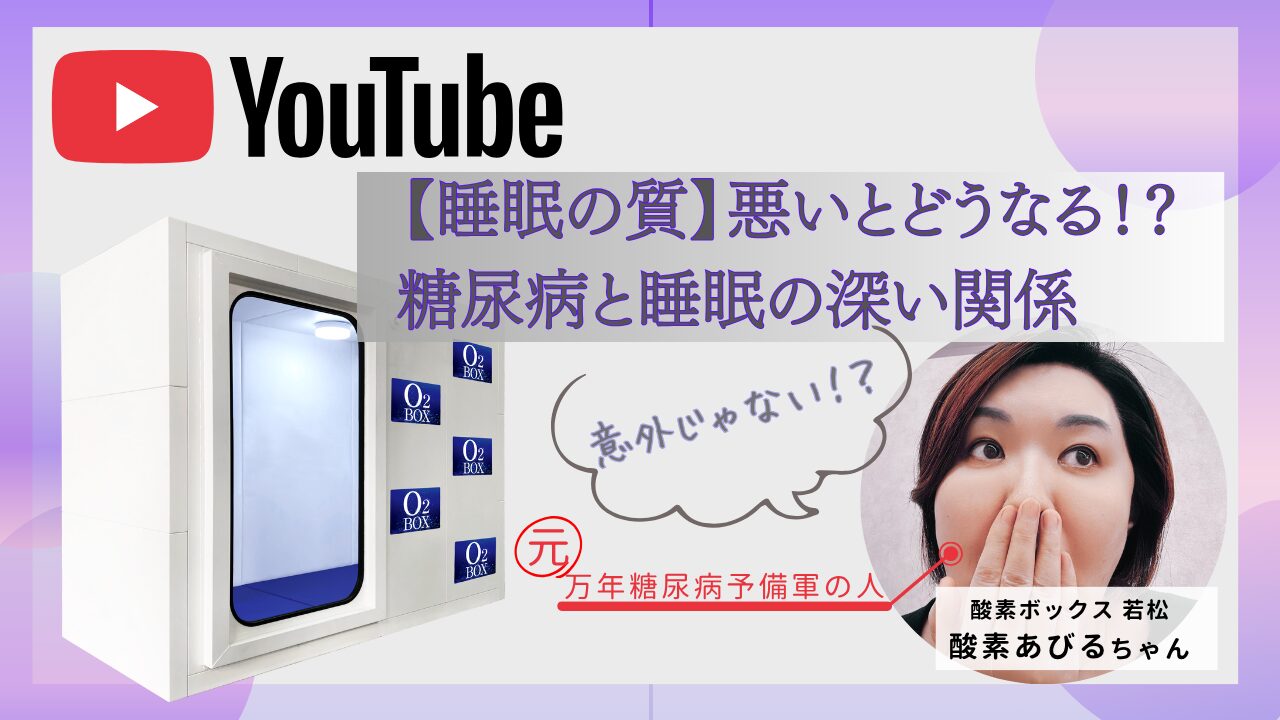
寝不足の日に限って、甘いものがやたらと食べたくなったり、普段より食欲が止まらなくなったりしませんか?
頭はぼんやりして、体はだるい
それなのに、なぜか食べ物を求めてしまう――
それは、意志の弱さではなく、体がSOSを出しているサインかもしれません
睡眠不足になると、糖の使われ方が変わります
研究では、睡眠時間が短い人ほどインスリン感受性が低下しやすく、結果として糖をエネルギーに変える力が弱まることがわかっています
インスリンとは、血液中の糖を細胞の中に取り込むよう指令を出すホルモンです
インスリン感受性が高いほど、少ない量のインスリンで効率的に糖を使うことができますが、感受性が下がると糖を取り込む反応が鈍くなり、血液中に糖が残りやすくなってしまうのです
本来、夜の眠りの間は副交感神経が優位になり、体は代謝を整えています
ところが寝不足が続くと、交感神経が優位なままになり、体は“戦闘モード”から抜け出せなくなります
その状態では、糖をうまくエネルギーに変えることができず、翌日の疲労感や甘いものへの欲求にもつながってしまうのです
ここで大切なのは、「睡眠時間」だけでなく「睡眠の質」です
眠りが浅いと呼吸も浅くなり、体に取り込まれる酸素の量が少なくなってしまいます
酸素が不足すると、糖を燃やすための材料が足りず、糖代謝の効率はさらに落ちていきます
まずは、できることから整えてみてください。
たとえば――
- 寝る前1時間はスマホを見ない(交感神経を刺激しない)
- 深い呼吸を意識して、体の緊張をほどく
この2つだけでも、睡眠の質は確実に変わります
そして、もう一歩先のサポートとして、【酸素ボックス】を上手に取り入れてみるのも良い選択です
気圧が高まる環境では血中の酸素分圧が上がり、全身の毛細血管に酸素が行き届きやすくなります
酸素が十分に満たされることで、眠りが深くなり、糖をエネルギーとして使いやすい体へと整っていくのです
糖をため込む体から、しっかりと燃やせる体になることで、より、睡眠の質が整い、代謝が変わる――
という好循環へとシフトしていきます
【糖尿病予備軍】食事制限でストレスたまってない!?
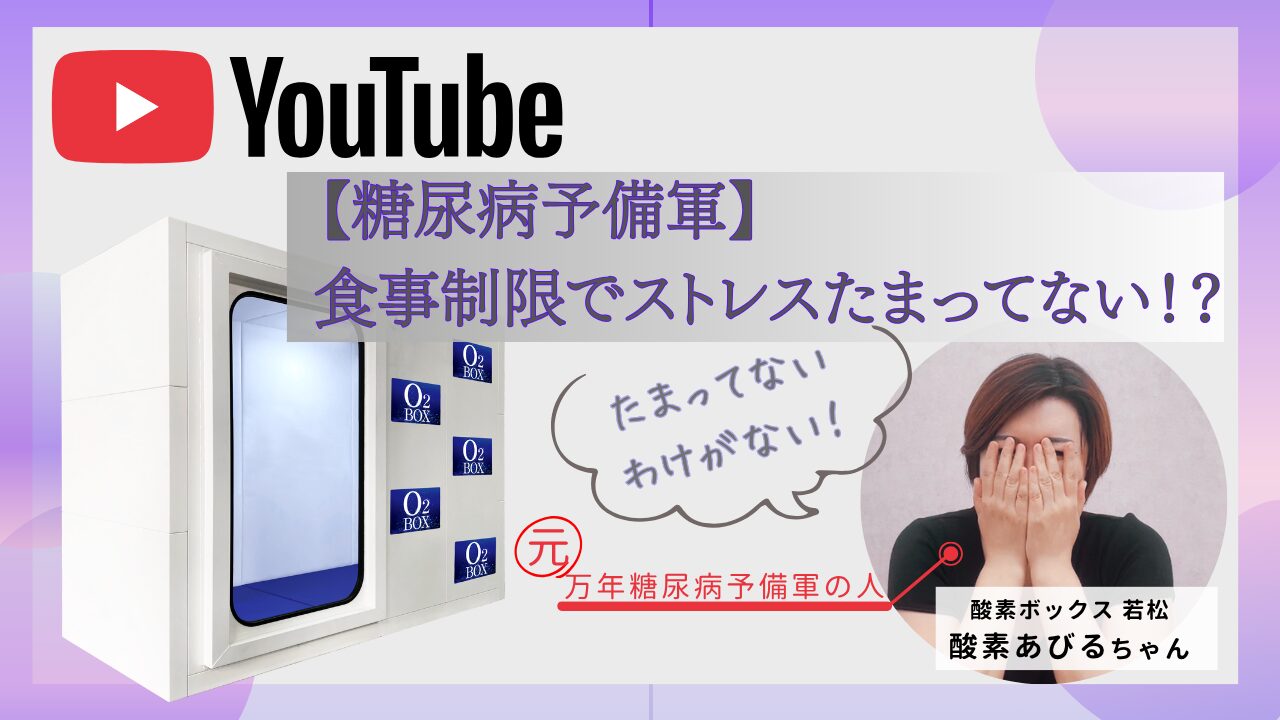
「食べたいものが食べられない」
「血糖値を気にしすぎて、ストレスがたまっている」
そんな声を、よく耳にします
我慢を続けているのに、数値が思うように下がらないと、心が先に疲れてしまいますよね
でも実は、ストレスそのものが血糖値を上げる原因になることをご存じでしょうか
ストレスを感じると、脳は“危険”を察知して、コルチゾールやアドレナリンといったストレスホルモンを分泌します
これらのホルモンは、肝臓に働きかけて糖を放出させるため、血糖値を一時的に上げるよう体に指令を出します
つまり、血糖を下げるために頑張っているその努力が、ストレスを通じて逆に血糖を上げてしまう――
まさに本末転倒な状態が起きてしまうのです
さらに見逃せないのが、ストレスと酸素の関係です
強いストレスを受けると、呼吸は浅くなり、体の酸素量が減ります
酸素が不足すると自律神経が乱れ、交感神経が優位になることで、血糖を上げやすくする原因のひとつとなるのです
つまり、ストレスによる血糖上昇の裏側には、いつも「酸素不足」が隠れています
血糖値を安定させるためにまず必要なのは、厳しい食事制限や過度な運動ではなく、深呼吸をして呼吸の質を良くして、酸素のめぐりを整えること
脳と体に酸素を届けるイメージで、ゆっくりと深く息を吸ってみてください
それだけで自律神経のバランスが整い、ストレスホルモンの分泌もやわらいでいきますよ
そして、【酸素ボックス】のように全身へ酸素を行き渡らせる時間をつくることも、ストレスの軽減と血糖安定の両面にプラスの作用をもたらします
頑張り続けてストレスをためるるより、まずは体をゆるめましょう
酸素の力を味方にすれば、心も体も自然なリズムを取り戻し、我慢しなくても血糖コントロールがようになっていきますよ
【9割が気づいていない】冷えがもたらす、糖尿病予備軍の危機
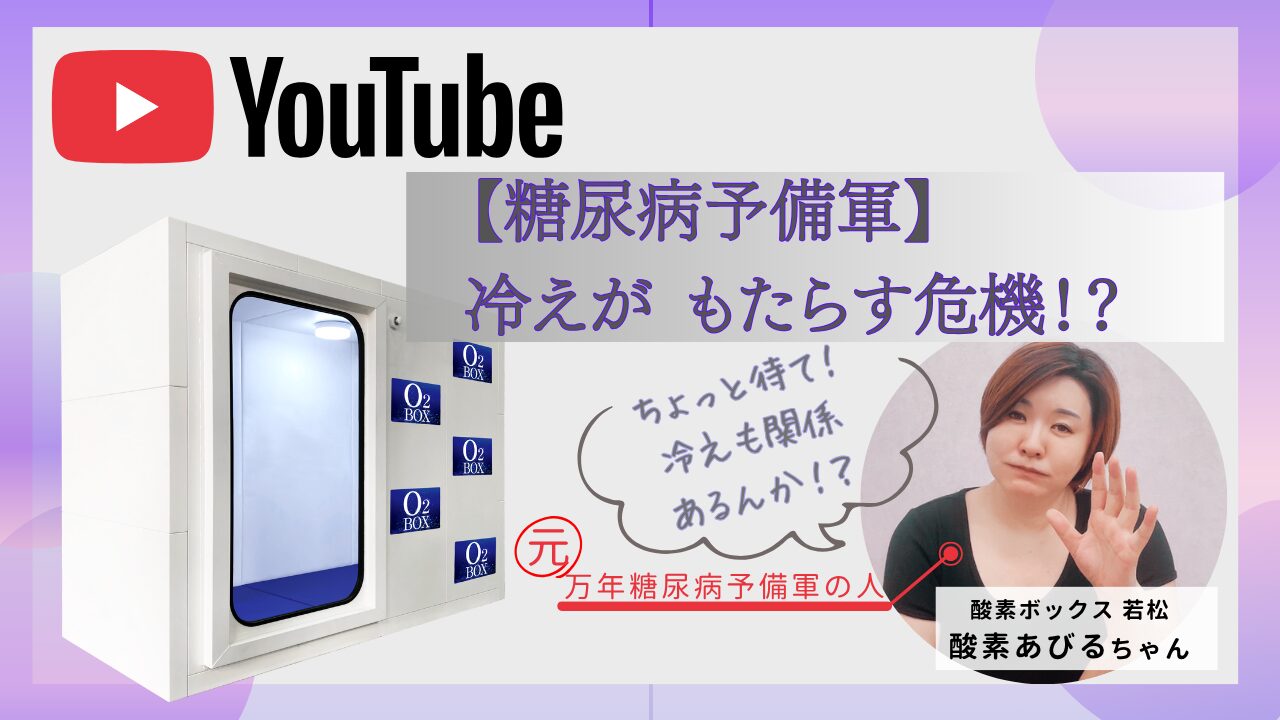
手足が冷たい
体の芯まで冷えている気がする
そんな日は、血の巡りまで滞って、なんとなく動くのが億劫になりませんか
実は、「冬になると血糖値が上がる気がする」という声は珍しくありません
感覚的なものに思えても、これは医学的にも根拠のある現象です
冷えと血糖値には、深い関係があります
体が冷えると、血管が収縮して末梢の血流が低下します
血のめぐりが悪くなると、全身への酸素供給が減り、筋肉や臓器での糖代謝――つまり、糖をエネルギーに変える力――が落ちてしまうのです
さらに、冷えによる酸素不足は、脳を“ストレス状態”だと錯覚させます
その結果、コルチゾールやアドレナリンといったストレスホルモンが分泌され、肝臓に「血糖を上げろ」という指令を出してしまいます
つまり、冷え=酸素不足=ストレス反応=血糖上昇という悪循環が起きやすくなるのです
(※生理学的研究でも、冷えが交感神経を刺激し血糖上昇を促すことが報告されています)
血糖を安定させるには、単に体を温めるだけでなく、血のめぐりを良くして酸素の供給を促すことが何より大切です
まずは、深呼吸
酸素を体のすみずみまで届けるイメージで、しっかり吐いて、ゆっくり吸って、しっかり吐く
それだけでも毛細血管の血流が整いはじめます
さらに、軽いストレッチやウォーキングで筋肉を動かすと、血流が高まり、自然と代謝のスイッチが入ります
そして、もうひとつのサポートが【酸素ボックス】です
高気圧・高濃度の酸素環境に身をおくことで、普段の呼吸だけでは届きにくい末梢の毛細血管や筋肉の奥まで、酸素が行き渡りやすくなります
日常生活の中で不足しがちな“酸素のめぐり”を補うサポートとして、冷えや血糖のコントロールが気になる方に選ばれているのです
【酸素ボックス】は治療ではなく、体内環境を整える健康器具です
「冷え」「疲れ」「代謝の鈍り」に悩む方には、頼もしい味方になるでしょう
酸素がしっかりめぐる体になると、手足の冷えだけでなく、血糖コントロールもゆるやかに落ち着いていきます
頑張りすぎず、体の仕組みを味方にして――
寒い季節も、穏やかに、あなたのペースで整えていきましょう
-
- 食事・運動・睡眠・呼吸――
-
- どれも私たちが「血糖」をコントロールするために欠かせない日常の営みです
-
- そして、そのすべてを支えているのが「酸素」です
-
- 体の奥で働く、この見えない存在が
-
- 代謝のリズムをつくり、心の安定を守っています
-
- 頑張る必要はありません、めぐらせるだけ
- その視点が、これからの血糖ケアを変えていく鍵になるでしょう
まとめ
- 食べることも動くことも呼吸することもすべては代謝の循環でつながっている
- 糖は燃料であり酸素はその燃料を燃やすための火種である
- 酸素が不足すると糖は使いきれず血液の中に滞る
- 糖を減らすより糖を使える体を整えることが血糖コントロールの鍵になる
- 筋肉と脳は体内で最も多くエネルギーを消費する器官である
- 酸素が十分に届くことで筋肉と脳は糖を効率的に使える
- 食事と運動の目的は糖を減らすことではなく酸素とともに燃やすことにある
- ヘモグロビンは酸素の運び手であり糖が多いとその働きが鈍くなる
- 酸素ボックスは酸素の通り道を整え代謝を底上げする環境をつくる
- 睡眠の質が下がると酸素が不足し糖の使われ方が乱れる
- ストレスは呼吸を浅くし酸素を減らし血糖を上げやすくする
- 冷えは血流を滞らせ酸素の供給を妨げる
- 深い呼吸は自律神経を整え酸素と血糖のリズムをそろえる
- 頑張るより巡らせるという視点が体の仕組みを生かす
- 酸素は努力の先にあるものではなく心と体をつなぐ静かな味方である
糖尿病対策について、「酸素」を起点にお話ししてきました
酸素を全身に届けるサポートとして、いま注目されているのが【酸素ボックス】です
気圧を少し高めた空間に入ることで、血液中の酸素量が増え、毛細血管のすみずみまで酸素が届きやすくなります
その結果、代謝や血流のめぐりが整い、血糖コントロールにも良い影響を与えると考えられています
糖を減らす努力ではなく、酸素を巡らせる工夫へ――
体の仕組みに寄り添う新しいケアの形です
酸素の力を味方につけて、もっと気楽に血糖コントロールをしたいと思った方は、わたくし、酸素あびるちゃんが愛してやまない【酸素ボックス】の記事をぜひご覧ください
酸素ボックスは医療機器ではない!|医療用酸素療法との違いと注意点を徹底解説
ヘモグロビンA1c(HbA1c) を下げるには?|酸素ボックス体験談
酸素ボックスが注目される知られざる理由|結合型酸素と溶解型酸素の違いとは?