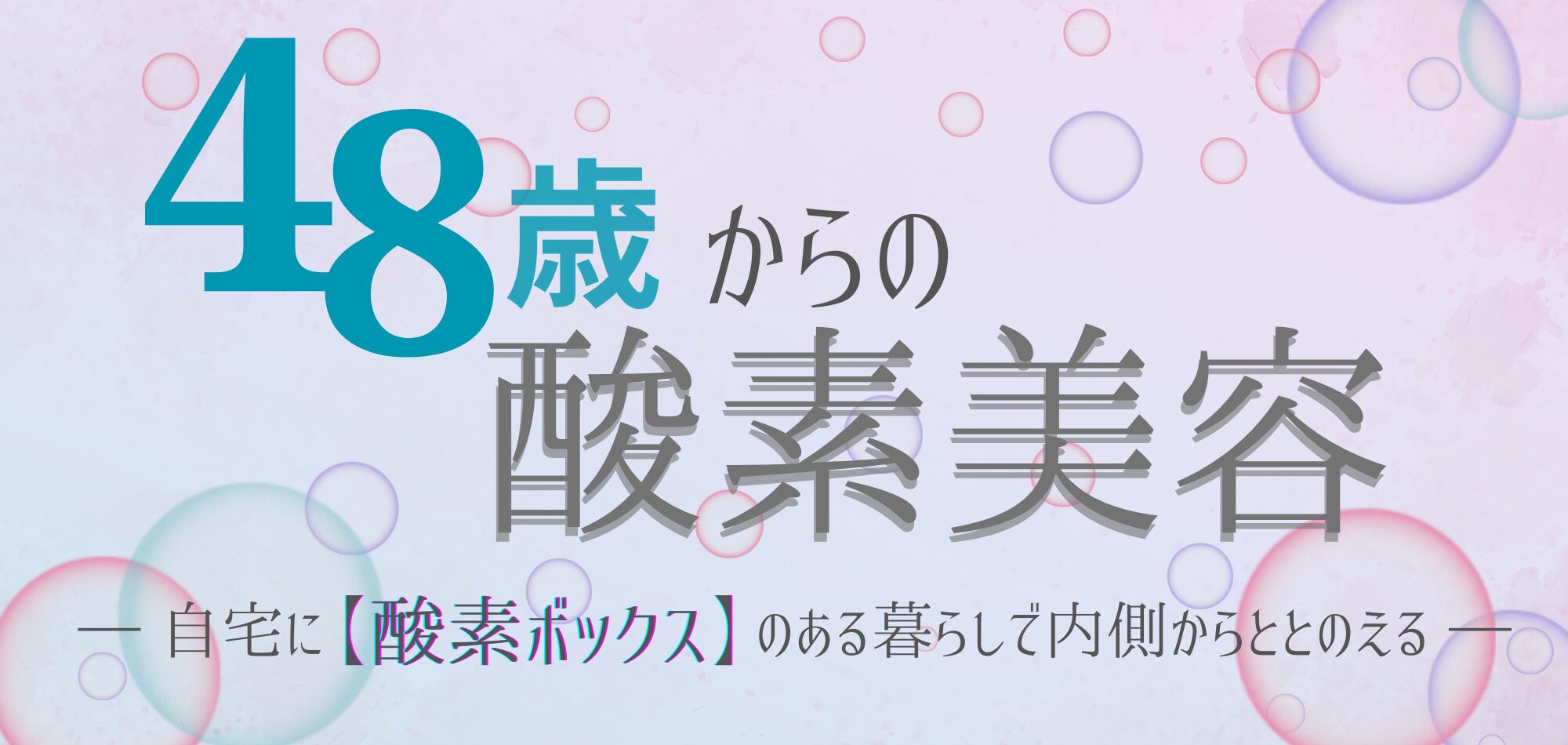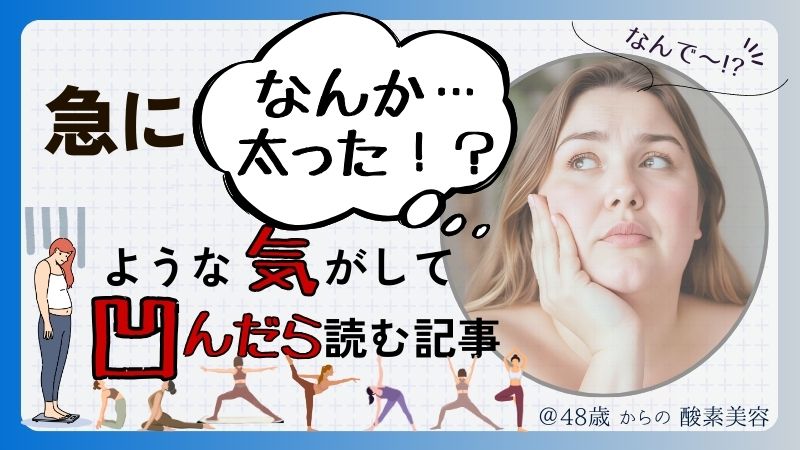
そもそも「むくみ」とは何か?|どんな状態を指すのか?

むくみ=余分な水分や老廃物の滞り
むくみとは、血管やリンパを通じて流れていくはずの水分や老廃物が、皮膚やその下にたまった状態のこと
血液やリンパの流れが悪くなり、本来なら尿や汗として外に出るはずの余分な水分や老廃物が体に残ってしまっているサインともいえます
朝起きたときに顔が腫れぼったく感じる、夕方になると靴がきつくなるのは、余分な水分がとどまり、腫れやふくらみとして表れているからです
美容面では、実際の体重以上に太って見えたり、疲れや老けた印象を与えたりする原因につながります
多くの女性が経験するむくみは、病気ではなく生活習慣や体質、ホルモンバランスの影響による一時的なものが大半です
だからこそ、日々の過ごし方や小さな工夫で軽減できる余地が大きいのではないでしょうか
一時的なむくみと慢性的なむくみの違い
一言に「むくみ」といっても、その状態には大きく二つのタイプがあります
ひとつは、一時的なむくみ
一時的なむくみは、誰もが経験するごく身近なものではないでしょうか
長時間の立ち仕事やデスクワーク、塩分の多い食事、睡眠不足などで一時的に水分が滞るもので、休養をとったり、軽く体を動かしたりすると数時間から一日で改善するケースが多いのが特徴です
代表的なのは 朝の顔のむくみ と 夕方の脚のむくみ
朝は横になっている間に体の水分が上半身にたまりやすく、特に顔やまぶたに出やすいですよね
夕方は一日中立ちっぱなしや座りっぱなしでいることで下半身に水分がたまり、足首やふくらはぎがパンパンになってしまいます
また、塩分の多い食事 をとった翌日は、体が水分をため込みやすくなるため、むくみが強く出やすいです
さらに、睡眠不足やストレス で自律神経のバランスが乱れると、血流やリンパの働きがうまくいかず、顔や脚のむくみを引き起こすこともあります
このような一時的なむくみは、休養や適度な水分補給、軽い運動やストレッチなどで改善しやすいのが特徴です
だからこそ、日常のちょっとした習慣がむくみの出やすさを左右するといえるのです
もうひとつは、慢性的なむくみ
むくみが、毎日のように続いたり、軽い生活習慣の見直しではなかなか改善しなかったりするタイプです
体質やホルモンバランスの影響、筋肉量の不足、生活習慣の積み重ねが背景にあることが多く、美容面でも疲れた印象や体型の崩れにつながりやすいので注意が必要です
さらに、慢性的な むくみの中には、生活習慣や体質だけでなく、心臓や腎臓などの不調が関係している場合もあります
いつもと違う強いむくみが続く、片側だけが腫れる、息切れやだるさを伴うなどの症状があるときは、自己判断や、美容ケアで済ませずに、医療機関で相談することも大切です
自分のむくみタイプをセルフチェック
むくみは誰にでも起こる身近な症状ですが、気づかないうちに慢性化している場合もあります
まずは日常の中でできる簡単なセルフチェックで、自分のむくみタイプを知っておきましょう
朝の顔と夕方の脚に注目
朝起きたときに顔が腫れぼったく、まぶたが重いと感じる人は「上半身に水分がたまりやすいタイプ」かもしれません
ただし昼までに自然に引いているなら一時的な範囲です
夕方になると靴がきつくなったり、脚がだるく感じたりする人は「下半身に水分がたまりやすいタイプ」といえます
帰宅して休んだあと、数時間で軽くなるなら大きな心配はいりません
指で押して跡が残るかどうか
すねや足の甲を指で軽く押してみて、数秒たっても跡が戻らない場合は むくみが強いサインです
靴下のゴムの跡も、これに該当するでしょう
数分から数時間のうちに跡が消えるなら一時的なむくみと考えられます
指輪や靴が窮屈になる
普段と同じサイズの指輪が外しにくい、夕方になると靴が窮屈に感じるといった変化もチェックポイントです
夜の入浴や睡眠を経て翌朝には解消しているなら一過性で心配ありません
注意ポイント
これらのサインが数時間〜翌日には改善するなら多くの場合は心配はいらないでしょう
ただし、むくみが数日以上続く、片側だけ強く出ている、息切れやどうにもならない疲れを伴うといった場合は、症状を軽視せず医療機関に相談してくださいね
女性に多いむくみの実態|厚生労働省の統計から見る傾向
「むくみ」は、女性に多い悩みのひとつです
厚生労働省の調査では、女性の およそ4人に1人 が「冷えやむくみ、だるさ」を気になる症状として挙げています
また別の調査では、約半数の女性が脚のむくみやだるさを自覚 しているという結果も出ています
研究によると、女性は男性に比べて むくみを感じやすく、その割合は 2倍以上 にもなるといわれています
特に脚のむくみは日常的に出やすく、週に4〜5日も自覚する人が少なくありません
さらに月経周期によっても、むくみの出方は変わります
排卵後の黄体期から生理前にかけては、ホルモンの影響で体が水分をため込みやすく、顔や脚のむくみを感じやすい時期です
また、生理が始まった直後は、血流の変化やホルモンのゆらぎから、一時的にむくみが強く出る人もいます
むくみは、誰にでも起こることだからと軽く見がちですが、放っておくと日常的な疲れや慢性的な不調につながることもあります
だからこそ「自分は、どんな原因で、どのタイミングで むくみやすいのか」を知り、早めに予防・対策をとることが大切なのです
美容面に与える影響|太って見える・老けて見える
むくみは水分が体にたまることで、体重が一時的に増えることもあります
ただしそれは脂肪ではなく余分な水分によるものなので、排出されれば数時間から数日で元に戻るのが特徴です
それでも顔や脚のシルエットはすぐに崩れてしまうため、実際の体重以上に太って見えてしまうのが厄介なところです
太って見える理由
顔に水分がたまると、輪郭がぼやけてフェイスラインが崩れ、二重あごのように見えることがあります
脚では、ふくらはぎや足首のラインがなくなり、スリムなパンツやブーツがきつくなることも少なくありません
実際の体重は変わっていなくても、シルエットが膨張して見えるため「太った?」と誤解されやすいのです
老けて見える理由
血液やリンパの流れが滞ると、肌の血色が失われ、くすみやクマが濃く見えます
目元やほうれい線のまわりに余分な水分がたまると、一時的にはふくらんでハリが出たように見えることもあります
しかし水分が引いたあとには皮膚がゆるみ、シワやたるみが強調されて見える原因につながります
その結果、実年齢よりも疲れた、老けた印象を与えてしまいます
メイクのノリが悪い、夕方にはファンデーションがよれてくる、靴が窮屈で歩きづらいなど、日々の生活でも軽い支障をきたします
例えば、午前中はむくみで顔が丸く見え、午後には水分が引いて、頬や目まわりがやつれたように見えるなど、一日の中でも印象が変わりやすいのも厄介なところでしょう
鏡を見るたびに違和感を覚え、自信まで揺らいでしまうこともあるのではないでしょうか
むくみを引き起こす主な原因
むくみは、一時的に起こることが多いものの、その背景にはさまざまな要因が関わっています
血液やリンパの流れ、食生活や水分バランス、自律神経やホルモンの働き、さらには筋肉量や生活習慣の違いによっても左右されるのです
ここでは代表的な原因を取り上げ、それぞれがどのようにむくみを招くのかを見ていきましょう
血行不良・リンパの滞り
血液やリンパは、体のすみずみまで酸素や栄養を届け、不要になった水分や老廃物を回収する役割を担っています
ところが血行が悪くなると、余分な水分や老廃物の回収が滞り、皮膚や皮下にたまって むくみとなって表れてしまいます
特に長時間同じ姿勢でいると、血流やリンパの流れが下半身に滞りやすくなりますよね
デスクワークや立ち仕事で夕方に脚がパンパンに感じるのは、その典型的なサインでしょう
また、冷えも血行不良を招く大きな要因です
体が冷えると血管が収縮して流れが悪くなり、水分や老廃物がうまく押し流せなくなります
その結果、顔や手足にむくみが出やすくなるのです
血液やリンパの流れを整えることは、むくみ解消に欠かせない大切なポイントといえるでしょう
▶対策のポイント
- 湯船に浸かる、温かい飲み物をとる、首や足首を冷やさないなど、体を内側から温める工夫を
- 1時間に一度は立ち上がって体を伸ばす、軽く歩くなど、座りっぱなしを防ぐ習慣を
- ふくらはぎや足首をやさしくマッサージ、足先のグーパー運動などで巡りをサポート
塩分・水分バランスの乱れ
私たちの体は、常に体内の塩分(ナトリウム)と水分のバランスを保とうとしています
ところが、塩分の多い食事をとると、体はその濃度を薄めようとして水分を余分にため込むようになります
このとき、血管の中の水分が外にしみ出しやすくなり、細胞と細胞のすき間(=組織間)に水分がたまってしまうのが「むくみ」の正体です
特にインスタント食品や加工食品、濃い味付けを好む方は、気づかないうちに塩分を多くとっている場合がありますので、気をつけましょう
逆に、「むくみたくないから」と水分を控えすぎるのも逆効果になることがあります
体が「水分が足りていない」と判断すると、抗利尿ホルモン(ADH)という物質が分泌され、尿としての排出を抑え、体内に水分をため込もうとするのです
その結果、皮膚の下に余分な水分が残りやすくなり、かえってむくみにつながってしまうこともありえます
特に女性は、生理前の黄体期や、塩分の多い外食後にむくみを感じやすい傾向があります
日常的にむくみやすい方は、「水分を控える」のではなく、こまめな水分補給と、塩分の取りすぎを見直すことがポイントです
目安としては、体重1kgあたり約30mlの水分がひとつの基準となります
※ 例えば体重50kgの方であれば、1日あたり1.5リットル程度を目安にすると良いでしょう(汗をかく量や季節によって増減させてOKです)
▶対策のポイント
-
外食や加工食品、スナック菓子などの塩分量を意識して控える
-
汗をかいた日は特に、ミネラルを含む水分をこまめに補給(※カフェイン飲料は利尿作用があるため注意)
-
目安は「体重1kgあたり30ml程度の水分」を一日に分けて飲むのが理想
-
カリウムを含む野菜や果物(バナナ・アボカド・ほうれん草など)を取り入れて、ナトリウムの排出を促す
自律神経やホルモンの影響
むくみには、体の中でバランスを保ってくれている「自律神経」や「ホルモン」も深く関わっています
自律神経とは、私たちの意思とは関係なく、呼吸や心拍、血流などを調整してくれる神経のことです
この自律神経には「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(リラックスモード)」の2つがあり、これらがバランスよく働くことで血流やリンパの流れもスムーズになります
しかし、ストレスや不規則な生活、寝不足などでこのバランスが崩れると、血管の収縮や拡張がうまくいかなくなり、血液やリンパの流れが滞りやすくなってしまうのです
これが、顔や脚などにむくみとして現れる一因になります
さらに女性の場合は、ホルモンの変動も大きな影響を与えます
とくに排卵後から生理前にかけての「黄体期」は、黄体ホルモン(プロゲステロン)の働きによって体が水分をためこみやすい状態になります
この時期は、体温が上がり、代謝も変化することで水分代謝が乱れやすく、顔や脚にむくみを感じやすくなるのが特徴です
また、生理前は気分が不安定になったり、イライラや眠気を感じたりと、自律神経もゆらぎやすくなります
こうした要因が重なることで、いつもよりも むくみが強く出てしまうこともあります
▶対策のポイント
-
自律神経の乱れを整えるには、深い呼吸・十分な睡眠・ぬるめのお風呂などが有効です
-
ホルモンの影響が出やすい時期は、体を冷やさず、無理をしない過ごし方を心がけてみましょう
-
また、イライラした日は意識的にゆっくりとした呼吸をして、リズムを整えることも大切です
筋肉量不足によるポンプ機能の低下
「筋肉は、見た目を整えるだけのもの」──そう思っていませんか?
実は、筋肉は“むくみ防止”においてもとても大事な役割を担っています
とくに注目したいのが「ふくらはぎ」
ふくらはぎの筋肉は、“第2の心臓”とも呼ばれています
歩いたり、足首を動かしたりすることで筋肉がポンプのように働き、下半身にたまった血液やリンパ液を心臓へ押し戻すサポートをしてくれているのです
しかし、運動不足や加齢により筋肉量が減ってくると、このポンプ機能が弱まり、血液や水分が足元にたまりやすくなってしまいます
とくに女性は、筋肉量がもともと少ないうえに、ヒールや長時間の座りっぱなし・立ちっぱなしの生活などが加わると、さらに循環が悪くなりがちです
筋力低下によって滞った水分は、夕方の脚の重だるさや、足首のくびれが消えるようなむくみとして現れやすくなります
▶対策のポイント
-
階段を使う、つま先立ちをする、スクワットを取り入れるなど、日常の中で足を意識的に動かす習慣を
-
長時間同じ姿勢が続くときは、ふくらはぎのストレッチやかかとの上げ下げがおすすめ
-
筋肉を育てるには「継続」がカギです、無理なく続けられる軽い運動から始めてみましょう
日常でできるむくみ解消法
「むくみは体質だから仕方ない」とあきらめていませんか?
実は、ちょっとした習慣の積み重ねが、むくみにくい体づくりにつながります
ここでは、今日からすぐに取り入れられる、日常生活の中でできるシンプルな解消法をご紹介します
水分補給と食生活の工夫
水分をとると「むくみそう」と思われがちですが、実は逆です
水分が不足すると体がそれを溜め込もうとして、かえってむくみやすくなります
ポイントは、こまめに、適量をとること、目安は「体重×30ml」程度
一気に飲むのではなく、朝・昼・夕に分けて摂るのがおすすめです
また、食生活も大切な要素です
塩分の多い食事はむくみの大敵!
外食や加工食品ばかりが続くと、知らないうちに塩分過多になってしまいます
カリウムを含む食材(バナナ、アボカド、ほうれん草など)は、余分なナトリウムの排出を助けてくれるため、むくみ対策には心強い味方となります
ストレッチ・運動で巡りをサポート
体を動かすことは、むくみの根本的な改善に欠かせない要素のひとつです
特に脚の筋肉、なかでも”第二の心臓”と呼ばれるふくらはぎの働きは重要で、重力に逆らって血液やリンパ液を心臓に戻すための“ポンプ”のような役割を担っています
しかし、長時間同じ姿勢でいたり、運動不足が続いたりすると、このポンプ機能がうまく働かなくなり、下半身を中心に水分や老廃物が滞りがちになります
こうして蓄積された余分なものが、むくみとして目に見えるかたちで表れるのです
ストレッチや軽い運動は、筋肉にやさしく刺激を与え、巡りを促すきっかけになります
血流が整えば、体の内側からスッキリとした感覚が戻ってくるはずです
特別な運動でなくても、日常の中で少しだけ“動かす”意識を持つだけで、めぐりのリズムは少しずつ整っていきます
お風呂や温めケアで代謝を促す
むくみを軽減したいなら、冷えをそのままにしないことも大切なポイントです
体が冷えると血管が収縮し、血流やリンパの流れが滞りやすくなります
その結果、水分や老廃物の循環がうまくいかず、むくみにつながってしまうのです
そんなときに頼りになるのが「温めるケア」
湯船にゆっくり浸かることで、体の深部までじんわり温まり、血流がスムーズになります
入浴の目安は【38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分】、じんわり汗ばむくらいの温度が、体を芯から温めてくれます
特に下半身の冷えやすい女性には、脚をしっかり温めることがめぐりの改善に直結します
夏場も油断は禁物です
冷房による下半身の冷えや、冷たい飲み物・食べ物のとりすぎで、体の内側は思った以上に冷えていますので、暑い日でもシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯に短時間でも浸かる習慣を取り入れてみましょう
入浴が難しい日は、足湯や温熱グッズ、カイロなどで部分的に温めるだけでもOKです
「気持ちいい」と感じる程度の温度で、無理なく続けられる温活を習慣にすることで、めぐりの質も少しずつ変わっていきますよ
お風呂上りにには、水分補給を忘れないようにしましょう
セルフマッサージで流れを整える
血液やリンパの流れをサポートするために、セルフマッサージも効果的です
むくみやすい脚や顔など、気になる部分を軽くほぐすことで、巡りが整い、余分な水分や老廃物の排出が促されます
難しい技術や強い力は必要ありません
「やさしくなでる」「手のひらで包むように流す」といったシンプルな動きでOKですよ
脚のマッサージなら、足首からふくらはぎ、ひざ裏に向かって下から上へ流すようにします
顔は、あご先から耳の下、首筋にかけてのラインをやさしくなでてあげるのがポイントです
※この時、肌をこすったり皮膚が伸びるほどの圧をかけてはいけません (シミやたるみの原因になりますよ)
お風呂上がりやスキンケアのタイミングなど、体が温まっているときに取り入れると、より効果が高まります
日々のセルフケアの中に、ほんの数分でも自分の体と向き合う時間を作ってみてはいかがでしょうか
サプリ&漢方の活用|内側から整えるアプローチ
食事や生活習慣の見直しに加えて、栄養素を意識的に補うことも、むくみケアには効果的です
普段の食生活では不足しがちな成分を、サプリや漢方の力を借りて内側から整えていく方法も視野に入れてみましょう
カリウム:余分な塩分と水分の排出をサポート
カリウムは、体内のナトリウム(塩分)バランスを整え、余分な水分を外に出すのを助けるミネラルです
むくみが気になる人にとっては欠かせない成分のひとつといえるでしょう
不足しやすい人は、バナナ・アボカド・きのこ類などの食材とともに、サプリでの補助もおすすめです
マグネシウム&ビタミンB群:巡りを助け、代謝を整える
マグネシウムは、筋肉や血管の働きを支えるミネラルです
ビタミンB群は、水分代謝やホルモンバランスに関わる栄養素で、疲れやすさや冷えにも関連しています
現代女性はストレスや偏食で不足しやすいため、マルチビタミンやミネラルサプリで補うと良いでしょう
たんぱく質:水分保持のバランスを整える
意外かもしれませんが、たんぱく質も むくみと関係しています
血中のアルブミンという成分が不足すると、水分を血管内にとどめておく力が弱まり、むくみやすくなることも
ダイエット中でもたんぱく質はしっかり摂るよう心がけましょう
プロテインや高たんぱくの補助食品を活用するのもひとつの手です
漢方薬の力を借りる
体質に合わせてやさしくアプローチしてくれるのが漢方の魅力ですね
むくみ対策としてよく使われるのは以下の2つです
-
防已黄耆湯(ぼういおうぎとう):水分代謝を助け、余分な水分を外に出す働きがあり、体力があまりない人や疲れやすい人に向いています
-
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):血の巡りと水の巡りを整え、女性の冷え・貧血・むくみに広く使われる漢方で、ホルモンバランスが不安定な時期にも使われます
いずれも体質によって合う・合わないがあるため、自己判断ではなく薬剤師さんや漢方に詳しい専門家に相談するのが安心です
塩分は“減らす”だけでなく“排出を助ける”工夫を
塩分(ナトリウム)の摂りすぎは、体が水分をため込みやすくなる原因のひとつ
特に加工食品や外食メニューには、塩分(ナトリウム)が多く含まれているため、意識していないうちに摂取量が増えてしまいがちですから、気をつけたいところですね
また、むくみを防ぐには、「減塩」だけでなく、「ナトリウムの排出をサポートする栄養素」を上手に取り入れることが大切です
たとえば、カリウムを豊富に含む野菜や果物(ほうれん草、アボカド、バナナ、きゅうり など)には、余分なナトリウムの排出を助けてくれる働きがありますから、嫌いじゃなければ、積極的に取り入れたいですね
また、塩そのものの選び方にも工夫をオススメします
精製された塩は、ナトリウムがほとんどで、ミネラルのバランスが偏りがちです
一方で、「天然塩(天日塩や岩塩など)」には、カリウム・マグネシウム・カルシウムなどのミネラルがバランスよく含まれており、ナトリウムの作用をやわらげてくれる働きも期待できます
「減塩」を推奨されるのは日本特有ともいわれています
これは、海外では「塩」といえば天然塩が一般的で、日本ほど精製された塩(ナトリウム)が使われていないためと考えられます
ミネラルは身体にとって不可欠な栄養素です
そのため「減塩」と言うよりも、「減ナトリウム」と理解したほうが本質に近いのかもしれません
日々の食卓でも、塩を選ぶときには ミネラル豊富な天然塩 を意識してみると、むくみにくい体づくりに近づけるかもしれません
睡眠とリラックスで自律神経を整える
自律神経のバランスは、むくみに深く関係しています
特に交感神経が優位な状態が続くと、血管が収縮して血行やリンパの流れが悪くなり、体内の水分代謝が滞ってしまいます
たとえば、仕事や人間関係のストレス、長時間のスマホやパソコンの使用、カフェインや糖分のとりすぎ、寝る直前まで緊張感が抜けない生活などは、交感神経が高ぶったままになる原因になります
だからこそ、日々の中で「整える時間」を意識的にとることが大切です
睡眠の質を高める、好きな香りでリラックスする、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、あなたにとって心地よい時間を大切にしてみてください
また、起きる時間・寝る時間・食事の時間といった日常のリズムをなるべく一定に保つことも、自律神経の安定につながります
体内時計が整うことで、むくみにくいコンディションをつくる土台にもなるのです
さらに、自律神経が整うことは、血行や代謝がスムーズになり、疲れにくくなる、眠りの質が安定する、肌の調子が良くなるといった、むくみ以外の美容・健康面にもさまざまなうれしい変化が現れます
心と体のバランスを整えることは、美しさと健やかさを保つためのいちばんの近道です
「なんとなく不調」を感じやすい方こそ、毎日のリズムと心のゆとりを大切にしてみてくださいね
姿勢や座り方を意識する(長時間の同じ姿勢を避ける)
長時間、同じ姿勢でいることは、血液やリンパの流れを滞らせ、むくみを引き起こす大きな要因です
デスクワークや車の運転などで座りっぱなしが続く場合は、1時間に一度は立ち上がる、軽く歩く、体を伸ばすなど、こまめに体を動かすことを意識しましょう
また、先ほども述べましたが、座っているときにできる工夫として、足首の曲げ伸ばしや、かかとの上下運動を取り入れるのも効果的です
特にふくらはぎは”第二の心臓”とも呼ばれ、ポンプのように血液やリンパの流れを助けてくれる重要な部位です
デスクの下でも簡単にできる動きなので、意識的に取り入れてみてくださいね
▶ 対策のポイント
-
同じ姿勢が続くときは、1時間に一度は軽く立ち上がる・体を動かす習慣を持ちましょう
-
座ったままでもできる、足首の曲げ伸ばし・かかとの上下運動をこまめに行いましょう
-
血流のサポートには着圧ソックスの活用も◎
→ 長時間の立ち仕事やデスクワーク時におすすめです
→ 就寝時の使用は避け、日中の着用をオススメします
こうした日常の小さな積み重ねが、むくみにくい体づくりにつながっていきますよ
体を冷やさない暮らしの工夫
体の冷えは、血行やリンパの流れを鈍らせ、むくみを引き起こす大きな原因のひとつです
特に女性は筋肉量が少ないこともあり、手足の先や下半身が冷えやすい傾向にあります
足首・お腹・腰まわりなど、冷えやすい部分を意識的に温めるようにしましょう
※首・手首・足首の3首(さんしゅ)を冷やさないというのは、温活の基本ですね
レッグウォーマーや腹巻き、湯たんぽなどのアイテムを活用すると、手軽に体を冷やさずに過ごせます
カイロの使用も有用でしょう
また、夏場でも冷房で体が冷えがちな方は、素足を避ける・ひざ掛けを使うなど、足元だけでも温める習慣が効果的です
飲み物はなるべく常温や温かいものを選び、冷たい飲み物の摂りすぎには注意しましょう
さらに、生姜や根菜類、発酵食品などの“温活食材”を意識して食事に取り入れることも、内側からの冷え対策になります
自覚しにくい冷えこそが、じわじわと めぐりの悪さや、むくみをもたらすこともあるため、日常の中で「冷やさない意識」を持つことが大切ですよ
この記事は、国立長寿医療研究センターをHPを参考にして書かせていただいてます
ありがとうございます